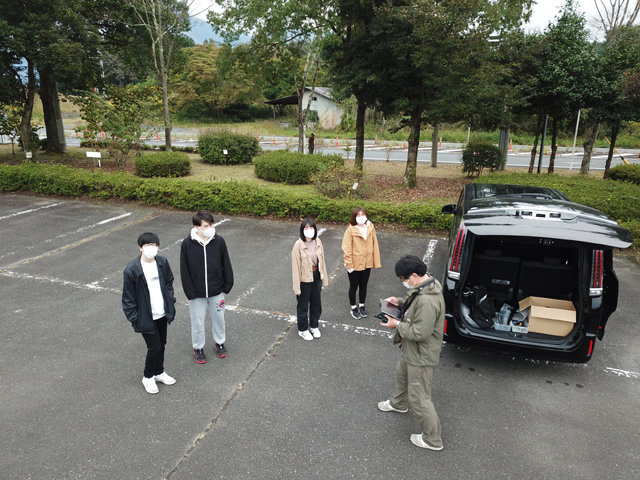|
|
 |
| 西武秩父駅での1枚。コロナ禍のため全員が狭い範囲に集まったのは西武秩父駅での集合の時だけでした。顔の写っていない人が3名いますが・・・ |
|
気候調査班は,実習初日に自記記録温度計を設置しました。盆地西側の丘陵の標高400m地点から,盆地底の標高200m地点を挟んで東の山地の標高700mまで,標高にして50mないし100m間隔で温度計を設置し,標高や東西斜面による気温の違いをみつけることを試みました。 |
| |
|
|
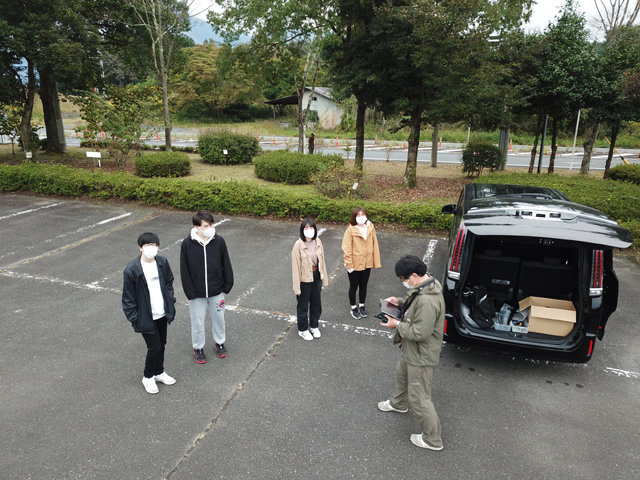 |
|
 |
| 気候調査班は,盆地底のグラウンドや丘陵頂部の公園で,日の出の前後にドローンを上げて標高25mごとの気温の観測を行いました。航空法を遵守して上空150mまでの観測ですが,標高200m地点と標高400m地点で観測を行ったので,標高200mから標高550mの気温の鉛直分布を観測することができました。 |
|
盆地には霧が出ていますが,高い位置にある煙突の煙は垂直に立ち上っています。さて,気温の鉛直分布にどのようになっていたでしょうか。 |
| |
|
|
 |
|
 |
| 河床礫の調査の様子です。河川の滑走斜面側と攻撃斜面側との比較や,河床の遷急点を挟んでの上流側と下流側など,地形に応じて礫の大きさにどのような違いがみられるかを調査しました。 |
|
現河床に近い段丘地形の構成物を調査しているところです。本流の河床堆積物と支流から出てきた土石流の堆積物の接点が露頭になって見えているようです。 |
| |
|
|
 |
|
 |
地すべりの移動体が荒川の河岸まで張り出したところを観ています。河岸に見えている岩盤はこの地域の基盤岩ですが,その上に地すべり移動体の一部が露出しています。露頭は荒川の対岸ですので残念ながら取り付くことができませんでしたが,離れた位置からスケッチなどを行って,観察結果を記録しました。
|
| |
|
|
 |
|
 |
| 露頭の調査をする前に,クリノメーターの使い方を学んでいる様子です。川の脇の土手に放置されたU字溝を地層の層理面に見立ててクリノメーターをあててみました。これによってクリノメーターの原理を理解しました。 |
|
高位段丘面を被覆するローム層が人工的に掘削されて出現した露頭を観ています。下の人の足下には段丘礫層が露出しており,上の人の足下にはテフラ層が露出しています。クリノメーターの傾斜計と巻尺を使って両者の比高を調べました。 |
| |
|
|
 |
|
 |
| 高位段丘面を被覆するローム層の土取場が放棄され,大規模な露頭となっていました。ここでは,層厚50cmに達する厚いテフラ層がローム層の中に2層みられたほか,層厚10~20cm程度の複数のテフラ層がみられました。これらのテフラが既知のどのテフラに対比されるかを明らかにするために,野外での岩相の記載を行いました。また,大学に持ち帰って分析するために,試料を採取しました。 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|