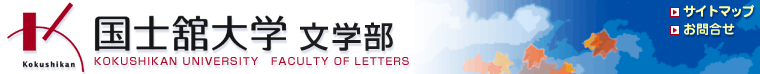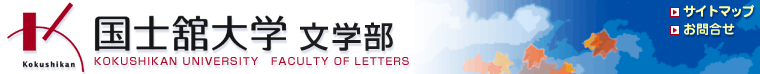| 第 1 号 〔昭和44年(1969年)3月〕 |
| 論 説 |
| 尾形 裕康 |
明治以前の社会教育 |
| 阿部 秀夫 |
理性の限界
−道徳の混乱に当面して− |
| 村田 正志 |
南朝関係 五条家文書の研究 |
| 大橋 與一 |
ロシア平原開発過程におけるロシア−
スラヴ人の動向と森林・河川の影響 |
| 高田 真治 |
東洋に於ける政治哲学の二源流
−孟筍二子の所論を中心として− |
| 岩井 良雄 |
「我禰・香二・師可・毛我」考
−「か」の清濁に関連して− |
| 研究報告 |
| 黒田 省三 |
対馬古文書保存についての私見 |
| 黒板 昌夫 |
対馬に於ける遺跡保存についての私見 |
| 村田 正志 |
宗氏歴代画像目録 |
| 学事彙報 |
第 2 号 〔昭和45年(1970年)3月〕 |
| 論 説 |
| 前野喜代治 |
吉田松陰 留魂録の研究 |
| 木村伊勢雄 |
現代文明の危機と新しい宗教
−シュヴァイツアー、ラッセル、トインビーの思想を中心にして− |
| 藤木 邦彦 |
奈良・平安朝における皇親賜姓について |
| 曽我部静雄 |
上計吏と朝集使 |
| 冨田 芳郎 |
台湾の鎮郷集落型の成立と分布について |
| 原田 種成 |
貞観政要の研究補遺 |
| 大窪 梅子 |
万葉の寄物抒情歌
−植物を主として− |
| 研究報告(当文学部関係教職員、本学年度刊行の著書報告を対象、以下同断) |
| 林 秀一 |
市川本太郎著「原始儒教の道徳思想」 |
| 横山 貞裕 |
曽我部静雄著「律令を中心とした日中関係史の研究」 |
| 藤井 秀夫 |
北方騎馬民族の足跡を探る |
| 学事彙報 |
第 3 号 〔昭和46年(1971年)3月〕 |
| 論 説 |
| 小林 高記 |
少年院における処遇と矯正教育 |
| 馬場 文翁 |
道徳教育の必要 |
| 森 純吾 |
教育権についての考察 |
| 黒田 省三 |
中世対馬の知行形態と朝鮮貿易権
−「宗家判物写」の研究− |
| 横山 貞裕 |
唐代の馬政 |
| 山本 正一 |
東京内湾特に東海区における海苔養殖 |
| 市川本太郎 |
随の大儒文中子の思想 |
| 春名 好重 |
古代・中世の漢詩・和歌の懐紙 |
| 研究報告 |
| 小久保崇明 |
岩井良雄著「日本語法史」
−奈良・平安時代編− |
| 酒井 忠夫 |
多賀秋五郎編著「近世東アジア教育史研究」 |
| 野地 潤家 |
西尾邦夫著「国語教育と話しことばの創造」
−劇の学習− |
| (別冊) |
| 藤井 秀夫 |
北方騎馬民族の足跡を探る(二) |
| 学事彙報 |
第 4 号 〔昭和47年(1972年)3月〕 |
| 論 説 |
| 尾形 裕康 |
明治の学制と新島襄
−五年の「学制」を中心として− |
| 大類 純 |
仏教における戦争観と平等観の倫理思想 |
| 小倉 竹治 |
我国における学校職業指導の発達過程 |
| 黒板 昌夫 |
大和郡山城とその城下町試論 |
| 小岩井弘光 |
宋代就糧禁軍について |
| 岩田 孝三 |
板谷峠における上杉(米沢)藩グラシー(Glacis)の政治地理的研究 |
| 山崎 道夫 |
崎門学派における近思録の尊重と若林強斎の近思録十四目講義 |
| 研究報告 |
| 浅井 得一 |
内田寛一著「近世農村の人口地理的研究」 |
| 市川本太郎 |
春名好重著「近衛家伝来国宝大手鑑解説」 |
| 竹内金治郎 |
若浜汐子(大窪梅子)著「万葉旅情」を読む |
| 水原 一 |
今成元昭著「平家物語流伝考」 |
| 学事彙報 |
第 5 号 〔昭和48年(1973年)3月〕 |
| 論 説 |
| 下地 恵常 |
近代日本の教育における市民性の淘汰 |
| 渡辺寿伝治 |
共同性の構造
−特に成員性について− |
| 森 純吾 |
幼児教育の問題 |
| 大川 清 |
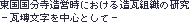 |
| 浅沼 操 |
鎧潟周縁地域における田地割替慣行の地理学的研究 |
| 今成 元昭 |
「聖」・「聖人」・「上人」の称について
−古代の仏教説話集から− |
| 稲垣 敏夫 |
ロシア語代名詞の分類 |
| 研究報告 |
| 仲 新 |
尾形裕康著「新版日本教育通史」 |
| 高橋 昌郎 |
大久保利謙編「森有礼全集」 |
| 中川 茂夫 |
大川清著「日本の古代瓦窯」 |
| 林 友春 |
多賀秋五郎著「近代中国教育史資料 清末編」 |
| 佐藤 定義 |
岩井良雄著「日本語法史 鎌倉時代編」 |
| 藤木 邦彦 |
春名好重著「寛永の三筆」 |
| 学事彙報 |
第 6 号 〔昭和49年(1974年)3月〕 |
| 論 説 |
| 前野喜代治 |
横井小楠の学問と思想 |
| 木村伊勢雄 |
現代とルソーの宗教思想 |
| 岡本 堅次 |
律令制初期の災害と政治
−慶雲期を中心として− |
| 山本 正一 |
明治初期諏訪湖開墾計画の歴史地理学的研究 |
| 鈴木由太郎 |
「焦氏易林」校注釈義 |
| 峯村 三郎 |
再び韻鏡の内外転に就て |
| 研究報告 |
| 石田加都雄 |
尾形裕康著「学制成立史の研究」 |
| 五十嵐正一 |
多賀秋五郎著「近代中国教育史資料 民国編上」 |
| 太田 三郎 |
板垣直子著「夏目漱石−伝記と文学」 |
| 萩谷 朴 |
春名好重解説「野辺のみどり」 |
| 学事彙報 |
第 7 号 〔昭和50年(1975年)3月〕 |
| 論 説 |
| 松本 良彦 |
価値観と倫理的相対主義 |
| 小倉 竹治 |
明治の哲学館事件 |
| 中山 八郎 |
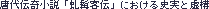 |
| 大橋 與一 |
北氷洋におけるロシア人の探検航海 |
| 西尾 邦夫 |
なさけ考 |
| 研究報告 |
| 藤井 貞文 |
大久保利謙著「岩倉具視」 |
| 大村 興道 |
多賀秋五郎著「近代中国教育史資料 民国編中」 |
| 横山 貞裕 |
光島督著「聖武天皇と正倉院御物」 |
| 竹内 常行 |
冨田芳郎著「台湾地形発達史の研究」 |
| 岩田 孝三 |
大橋與一著「帝政ロシアのシベリア開発と東立進出過程」 |
| 三浦 康弘 |
春名好重著「書の話」「日本書道史」 |
| 学事彙報 |
第 8 号 〔昭和51年(1976)3月〕 |
| 論 説 |
| 小林 高記 |
出席停止とその周辺の考察 |
| 大類 純 |
現代中国思想から観たフォイエルバッハ哲学批判 |
| 木下 三郎 |
理科教育の目標についての二・三の考察
(主として水栽培の問題との関連において) |
| 藤木 邦彦 |
平安時代における近陵・近墓の被葬者について |
| 横山 貞裕 |
魏と邪馬台国との関係について |
| 山本 正一 |
岩手県沢内村湯田町田野畑村の集落再編移転 |
| 市川本太郎 |
日本律令の刑罰と中国思想 |
| 板垣 直子 |
安部公房の文学 |
| 研究報告 |
| 小野 一成 |
尾形裕康著『こけむしろ』
尾形裕康博士業績目録・随想 |
| 米原 正義 |
村田正志編『出雲国造家文書』
島根県教育委員会編『出雲意宇六社文書』 |
| 吉田 寅 |
多賀秋五郎著『近代中国教育史資料 民国編下』 |
| 寺岡 龍含 |
市川本太郎著『孟子之綜合的研究』 |
| 佐藤 定義 |
岩井良雄著『日本語法史江戸時代編』 |
| 井村 君江 |
板垣直子著『文学概論』 |
| 学事彙報 |
第 9 号 〔昭和52年(1977年)3月〕 |
| 論 説 |
| 渡辺寿伝治 |
共同性の構造 |
| 佐々 博雄 |
熊本国権党と朝鮮における新聞事業 |
| 中山 八郎 |
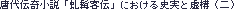 |
| 大崎 晃 |
成立発展期北洋母船式捕鯨 |
| 山崎 道夫 |
若林強斎の近思録十四目講義 |
| 大窪 梅子 |
玉藻考 |
| 大照 完 |
子どもの形式的推論の可能性について |
| 研究報告 |
| 森 郁夫 |
大川清著『下野古代窯業遺跡』 |
| 山崎 純一 |
多賀秋五郎著『近代中国教育史資料人民中国編』 |
| 学事彙報 |
第 10 号 〔昭和53年(1978年)3月〕 |
| 論 説 |
| 前野喜代治 |
本居宣長
−その教育者的側面− |
| 松本 良彦 |
現在の日本における哲学的倫理学 |
| 大志万準治 |
人間学序説
−総合的人間学をめざして− |
| 戸田 有二 |
地方官衙跡考 |
| 小岩井弘光 |
北宋末・南宋の就糧禁軍について
−宋代兵制史研究の一環として− |
| 山本 正一 |
集落移転再編 |
| 許勢 常安 |
上海中国書局印行と清議報訳載の「佳人之奇遇」を比較して
−特にその名訳と誤植訂正− 第二編 |
| 研究報告 |
| 小林 健三 |
前野喜代治著『佐久間象山再考』
−その人と思想と− |
| 高橋 昌郎 |
大久保利謙著『明六社考』 |
| 上坂 信男 |
今井卓爾博士著『物語文学史の研究全三冊』の紹介をかねて |
| 国東 文麿 |
今成元昭編『宗教と文学−仏教文学の世界』 |
| 学事彙報 |